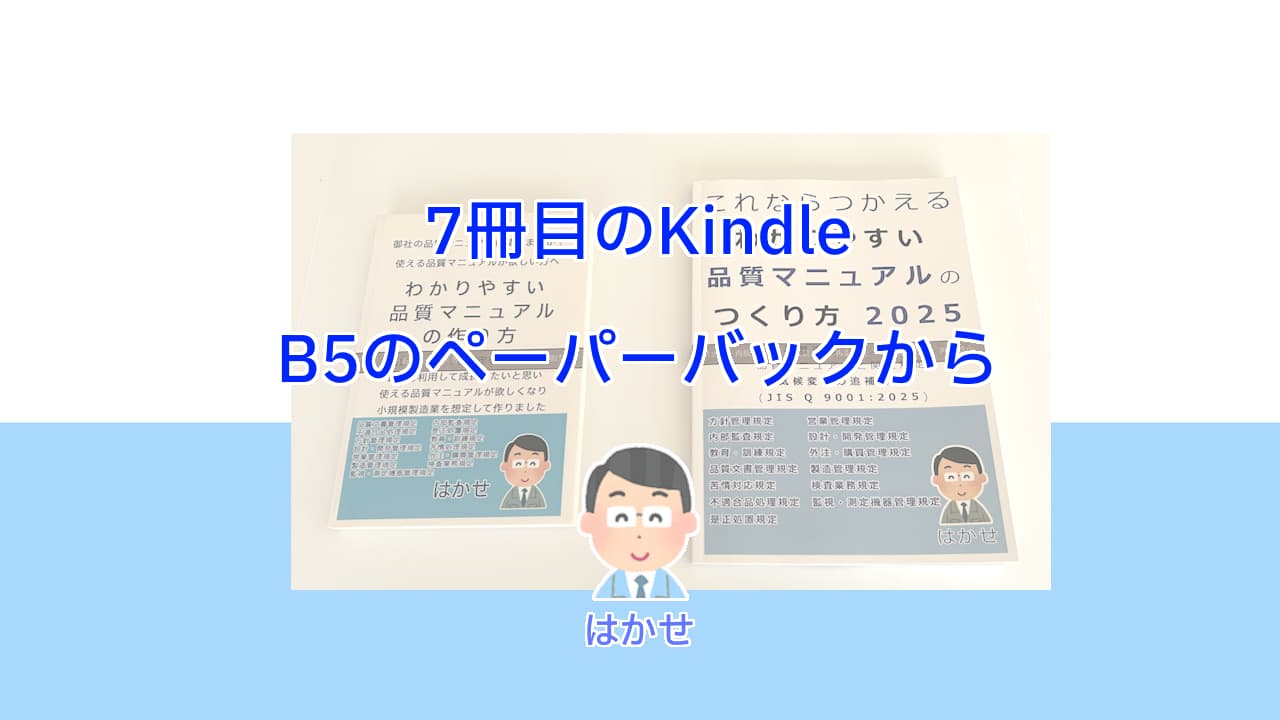Kindle出版はしばらくお休みかと思っていましたが、既刊「わかりやすい品質マニュアルの作り方」の続編を作ることにしました。
これまでの6冊、電子書籍のKindleを作ってから、紙の書籍(Kindleペーパーバック)を作っていました。
今回は、1ページの文書量を増やしたい、表を見やすくしたいと思い、これまでのA5判ではなくB5判で作ることにしました。
Kindleペーパーバックから作成したはじめての出版となるので、電子書籍化とペーパーバック作成について、具体的にどの様に進めたのかについて説明します。
Kindle本の原稿を書く:ブログ記事の作成
はじめに、既刊「わかりやすい品質マニュアルの作り方」の続編を作ることにした理由を列挙します。
- 既刊の全体的な見直しをすることで、2026年の品質マニュアル改訂前にやっておくべきことを明確にしたいので、見直しは必要と考えていた。
- 詳細は省きますが、JISQ9001:2025の追補が2024年3月に発行され、品質マニュアルの改訂が必要になった。
- ISO9001:2015の改訂作業が進んでいて、2026年の後半には発行される見込みとなっている。
実際見直してみると、大幅に加筆・修正を加えたい部分もあり、2025年版として作り直した方がよいとの結論になりました。
7冊目のKindle本、これまでブログ記事からの作成ではなく、既刊「わかりやすい品質マニュアルの作り方」のKindleペーパーバックの原稿(ワードファイル)を使い、次のように作っていきます。
- 既刊を見直し、変更(加筆・修正)が必要な部分を洗い出す。
- 関連するブログ記事を使い、既刊のワードファイルに加筆・修正を加える。
なお、表紙は2025年版ということがわかるように変更する。
(今回は対象外)ブログの記事作成・投稿
ブログの記事からKindle出版する場合には、ブログ記事作成時に、次のことを考慮します。
- 1つのカテゴリがKindle本の章になるイメージ
- ブログ記事をカテゴリ単位でまとめる際には、順番を意識する。
- ブログ記事のボリュームが、Kindle本として大き過ぎる場合には、複数の章に分ける
Kindle本としての構成を検討
今回は、既刊の加筆・修正ではありますが、新たに追加したい内容もあるため、全体構成やどこに追加したらよいかは事前に考えてから編集作業をはじめます。

ワードで170ページ程度あるので、作業内容をある程度整理してから着手しています。
行き当たりばったりで編集をはじめてしまうと、一気に終わる作業量ではないため、どこまで進んだか、何をしたのか分からなくなってしまいます。
作業内容を記録すればよいのでしょうが、それはそれで面倒ですし、ワードの校正機能などを使うのも1人での作業になるのでメリットよりも面倒だと感じてしまったのが正直なところです。
Kindle本としての構成を考え、作る時の考慮事項を列挙します。
- 「はじめに」は、つかみとして重要ですが、思い通りに進まないのもまた事実です。「気長にコツコツとアイディアをメモして、まとめてみる」を続けます。
- メインとなる章は、ブログのカテゴリを参考にして決める。
- 全体の章立て(構成、目次)を決める。
- 「おわりに」は、あわてなくていい。基本的に「はじめに」に対応する形でまとめればよい。
Kindleペーパーバックの書式設定
既刊はA5サイズでしたが、今回は次の理由でB5サイズとしました。
- 1ページの文書量を増やしたい。
- 表を見やすくしたい。(大きな表をできるだけ少ないページ数にしたい。)
フォントは見やすさ重視でメイリオとし、フォントサイズは10ptとしました。
ワードファイルの余白も変更になるので、既刊のワードファイルの編集をはじめる前に、B5サイズの本としての余白設定などを決めました。

後からでも変更はできるのですが、レイアウトを再度見直す必要があるので、できるだけ早い段階で決めた方がよいと思います。
見た目など、ある程度作業を進めないと分からない部分もありますので、その辺は悩み過ぎずに後で手を動かすことにしました。
タイトルと表紙デザイン
全体構成(目次)のイメージができてきたらタイトルと表紙のデザインに手をつけます。
- メインタイトル、サブタイトル
- キャッチコピーを含む表紙デザイン(イラストとか)
本文のボリューム(ページ数)が決まらないと、Kindleペーパーバックの表示の厚さが決まらないので、とりあえずブログ原稿をKindle本のワードファイルにまとめたらページ数を確認します。
Kindleペーパーバックの表紙データは、レイアウトがだいたい決まってからGIMPを使い仕上げていきます。

GIMPはとても多機能ですが、使い方を調べたのは文字の縁取りぐらいです。Kindle本は表紙デザインが重要だといわれていますが、ニッチな専門的な本になるのと、個人的にセンスがあるとも思えないのでデザインには、時間をかけ過ぎないようにしています。
はじめにとおわりに
「はじめに」は、意外に難しいというか、スムーズに仕上がっていくこともあれば、なかなか形にならない時もあります。
タイトル(書名)とキャッチコピー(表紙に加える)と合わせて、思いついたことをメモに残したりと工夫が必要です。
「おわりに」は、「はじめに」と対になる感じでまとめるようにしています。
Kindleペーパーバックを仕上げる
Kindleペーパーバックの表紙は、表、横、裏の表紙が1つになったものです。
Kindle本の原稿(ワード)のボリューム(文字数)が決まれば、ページ数が決まるので、グラフィック系のソフト(GIMP)で仕上げます。

私が使うGIMPのグラフィック系の機能は、文字やアイコンの縁取り程度です。
Kindle本(電子書籍)を仕上げる
Kindle本の原稿(ワード)は、Kindleペーパーバックのファイルを使っています。

今回は6冊目なので、構成が似ているKindle本のワードファイルを流用します。表紙も同様です。
Kindle本の文章は、
- ブログ記事
- ブログ記事をKindle本の原稿(ワード)にする時
- Kindle本の原稿(ワード)
の少なくとも3回は、推敲しています。
ブログ記事の文章としての仕上がり具合にもよりますが、Kindle本としてまとめると、誤字・脱字や日本語変換ミスだけでなく、表記ゆれも出てきます。
Kindle本の原稿(ワード)になってから、
- 推敲
- 文章の構成(順番を変更したり、追加・削除)
を繰り返していきます。
販売開始
Kindleペーパーバックから本文は作成しましたが、販売は今まで通り、電子書籍のKindleとKindleペーパーバックは、連続して行います。

Kindleペーパーバックは校正刷りで現物確認をしているため、同時販売しようとすると、電子書籍のKindle販売開始を遅らせることになります。
完成したら認知して頂くために、即販売開始がよいと考えていますので電子書籍のKindleが先行販売となります。
ブログによる紹介記事の準備も必要なので、事前にどこまで準備できるかがポイントです。
まず、電子書籍のKindleで申請し、販売開始できるようになったら、Kindleペーパーバックを申請します。

Kindleで販売開始にならないと、同じ内容のKindleペーパーバックも販売開始できないだろうと考えているからです。
価格を決める
価格を決める必要があります。
例えば、
- 電子書籍のKindleは、同じシリーズなので同一価格で、手に取りやすい価格設定にする。
- Kindleペーパーバックは、印刷代や送料を除いた価格設定にする。
と言った感じです。

ある程度売れるとKindleのキャンペーンのAmazonからお誘いがきます。認知されるのにもよいだろうと、キャンペーンには申し込む様にしています。
まとめ
これまでのKindle6冊は電子書籍のKindleを作ってから、紙の書籍(Kindleペーパーバック)を作っていました。
今回は、既刊「わかりやすい品質マニュアルの作り方」の続編となり、Kindleペーパーバックでの1ページの文書量を増やしたい、表を見やすくしたいと思い、これまでのA5判ではなくB5判で作りました。
Kindleペーパーバックから作成したはじめての出版となるので、電子書籍化とペーパーバック作成について、具体的にどの様に進めたのかについて、以下の項目で説明しました。
- Kindle本の原稿を書く:ブログ記事の作成
- (今回は対象外)ブログの記事作成・投稿
- Kindle本としての構成を検討
- Kindleペーパーバックの書式設定
- タイトルと表紙デザイン
- はじめにとおわりに
- Kindleペーパーバックを仕上げる
- Kindle本(電子書籍)を仕上げる
- 販売開始
- 価格を決める